第三話 反乱前夜(2)

人間たちの様々な思惑が渦巻くこのアンデスの地にも、季節だけはいつもと変わらずめぐっていく。
今年も夏がやってきて、アンデス高地のこのティンタ郡あたりにも、やっと緑豊かな季節が訪れていた。
この地を流れゆくビルカマユの川は、真っ青な空を映して、いっそう深い藍色に輝いている。
集落の道端に植わった柳やモイェの木々も、この地の短い夏の光を謳歌するように、緑の葉をいっぱいに広げて精一杯に陽光を受けていた。
濃い緑色に染まったジャガイモやトウモロコシ、キノアの畑がはるかに広がり、その間を黄緑色の牧草が谷間を埋めている。
自然からこれほど豊かな実りを授かりながらも、農民たちの手にはその一部すらも残りはしなかったのだが…。
それでも、税を納めねばならなかった。
それができなくなれば、それは死を意味する。
コイユールはささやかな畑で、丁寧に雑草を抜きとりながら、ジャガイモの葉の育ち具合を調べていた。
濃い緑色の葉は厚く、しっかりと成長している。
コイユールはその生命力を愛しく思った。

そして、軽く手の泥を払って、畑の中央に立ち、瞳を閉じた。
それから、畑全体を瞼の裏に思い浮かべた後、太陽と月のシンボルをイメージの中で描いて、そして、いつものようにマントラを3回唱えた。
そのまま静かに心を集中していると、上空からすっと光が降りてくる感覚があり、その光はコイユールの全身をめぐりはじめる。
そのまま彼女はイメージの中で、豊穣の祈りの思いをこめて自分の畑に光を送った。
イメージの中で、畑全体が光に包まれていく。
爽やかなそよ風が吹きぬけ、コイユールの頬をかすめていった。
緑の草の香りが風にのって、舞うように漂っている。
さらに、その閉じた瞳の奥で、光は、自分の畑を越え、隣の畑も包み、さらに、その隣の隣の畑に、そしてさらにはずっと遠くの平原を越えて、はるかコルディエラ山脈にも届くほどに広がっていく。
「コイユール!」
少し離れた所から、ふいに誰かが呼ぶ声が聞こえた。
コイユールはゆっくりと目を開いた。
あの時の少女、アンドレスの館であの夜出会った少女、マルセラがむこうの土手の方から手を振りながら元気に走ってくる。
「マルセラ!」
コイユールも笑顔で手を振り返した。
アンドレスの館で初めてトゥパク・アマルに出会った日の後も、アンドレスはコイユールに変わらず接した。
コイユールも、変わらず振舞っていた。
アンドレスがトゥパク・アマルの甥であったこと、つまり、皇帝末裔の血縁であったという事実は、確かに、彼女にとって、アンドレスとの間に隔絶的な距離感を突きつけてくるものではあった。
しかし、この国を思う気持ちは、とても似ていた。
それは身分や立場の違いを超えて、二人をさらに深い絆に導いていた。
そのアンドレスも、もう随分前に休暇も終わり、今は再びクスコの寄宿学校へと戻っている。
それから、あの夜に出会った少女マルセラと、たまたま年齢が近かったことや、同じ集落に住んでいたことなどもあり、こうして時々一緒に過ごすようになっていた。
マルセラはインカ族の貴族の娘で、トゥパク・アマルの腹心の部下の一人、先日の代官アリアガの館にも護衛として出向いていたあの鷲鼻の男、ビルカパサの姪であった。

まるで少年のような風貌をした少女で、短く切った黒髪をターバンでまとめ、いつもスカートをたくし上げて、すらりとした褐色の足でカモシカのように敏捷に動いた。
凛とした眼差しは、あのビルカパサ譲りであろう。
また、マルセラは、コイユールにとっては、よき「先生」のような存在でもあった。
貧しい農民のコイユールはまともな教育も受けることはできなかったが、貴族のマルセラはそれなりの教育を受けていた。
コイユールは、畑の端に大事そうに置いてあった、アンドレスからもらったあのスペイン語の教本を手に取った。
マルセラに聞きたい質問がたくさんあった。
「ねえ、マルセラ!」
コイユールが本を差し出しかけたのを、マルセラが素早く制する。
「それは、あと、あと!」
そして、コイユールの傍の土手に座ると、両手の平に乗るような石の塊を懐から取り出した。
周囲を削って星のような形に整えられた重そうな石で、中央に穴が開いている。
「それは?」
コイユールが不思議そうな顔をするのを、マルセラは「やっぱり、知らないのね。」と得意気な表情をつくった。
「あんたは、ほっんと、なんも知らないんだから」
それは、コイユールと会う時のマルセラの口癖である。
そして、「ほらっ」と、その星型の石をコイユールの手の平にポンと投げ渡した。
コイユールの手の平にズシリと重さが伝わる。
「重い…!
これ、何?」
「それは、オンダの石!」
そう言いながら、また懐から、今度は毛織の太い紐のようなものを取り出した。
「そんで、これは、そのオンダを振り回して投げるためのバンド!」
マルセラが、嬉々として言う。
コイユールは合点がいった。
それは、インカ時代から伝わる伝統的な武器、投石器(オンダ)だった。
恐らく、その星型の石の中央の穴にその紐を通して、振り回して勢いをつけ、石を敵に放つのだろう。

「これ、オジ様から、もらっちゃったのっ!!」
マルセラは叫ぶようにそう言うと、勢いよくコイユールを振り返った。
その目は、まるで星のようにキラキラ輝いていた。
多分、『オジ様』とは、あのビルカパサのことだろう。
「そ、そうなの。
良かったね!」
マルセラのその無邪気で、もう夢中な、少年のような様子がおかしくて、コイユールは思わず笑ってしまった。
「何が、おかしいのさ!」
マルセラが頬を紅潮させる。
それから、すっくと立ち上がって、再び瞳を輝かせてコイユールを見た。
「これ、投げてみようよ!!」
「ええ〜!」
さすがにコイユールも目を丸くした。
が、一度こうと決めたマルセラの勢いを止められないことを既に知っているコイユールは、彼女の手を取って、急いで畑のあたりから離れた広々とした空き地の方まで引っ張っていった。
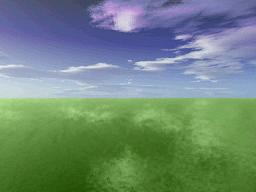
遠くの高台で、リャマの親子が二人の様子を見物している。
「じゃあ、行くわよ!!」
マルセラは興奮気味な目で、その星型の石の中央に紐を通した。
コイユールは周囲に人の気配がないことを確認し、それから、リャマの親子に間違っても石が飛んでいかないように、とマルセラに念を押した。
「そんなこと、わかってるわよ!
あたしの運動神経の良さ、見てなさい!!」
マルセラは鼻息荒くそう言うと、紐を通した石をブンブンと勢いよく振り回しはじめた。
コイユールは慌てて後ろに下がった。
「本当に、大丈夫…?」
マルセラの横顔は真剣そのものだ。
はるか前方の一点を鋭い眼差しで見つめている。
そして、高い掛け声と共に、石を放った。
石は素晴らしい勢いで宙を飛び、20〜30メートル先の草の上にドスンと落ちて、その辺りの草を削りながら激しく回転をした後、ゆっくりと止まった。
高台から見下ろしていたリャマの親子が、飛び上がるように走り去っていく。
マルセラは肩で息をはずませながら、爛々と瞳を輝かせていた。
額には、うっすらと汗を滲ませている。
コイユールは、思わずパチパチと手を叩いた。
「すごい!」
「でしょっ!!」
嬉々とした眼差しで、マルセラはこちらを見た。
が、その瞬間、「痛ぁっ!」と右手首をおさえながら、マルセラはその場にしゃがみこんだ。
コイユールが急いで彼女の手首を見ると、真っ赤に腫れている。
「ひねってしまったんだわ」
「いたぁぁ…」
マルセラは先ほどの雄姿はどこへやら、半べそで恨めしそうにオンダのバンドをみつめた。
コイユールは彼女をゆっくりと座らせた。
そして、そっと自分の手をマルセラの患部に添える。
今はコイユールのことを知っているマルセラは、素直にコイユールのするがままに任せた。
しばらくすると、マルセラは自分の手首のあたりに、柔らかなあたたかさが波動のように伝わってくるのを感じていた。
次第に、痛みが和らいでいく。
一方、コイユールはマルセラの手首に意識を向けながらも、どこかで、全く別のことを考えていた。
彼女は、先ほどのオンダ(投石器)のことを思った。
確かに、あの石がぶつかったら致命的な打撃になるのかもしれないけれど、だけど、それとスペイン人たちの所持しているピストルや大砲とは、とうてい比べ物にならない、というか何か非常に次元の違うもののように感じられた。
いや、実際、次元があまりにも違うのだ。
こうした差は、武器に限ったものなのだろうか…。
コイユールは心の中で、深い溜息をついた。
なにか、自分たちがとても小さく、無力に思えてくる。
コイユールはその思いを打ち消すように、首を振った。
そして、マルセラの患部に手を添えたまま、空を見上げた。
インカの神、太陽の輝く空は、彼女に希望を与えてくれるはずだ。
しかし、今日の空は妙に遠く、高く、まるでとても手の届かない異界のように、ただ漠々と広がっているだけだった。

同じ頃、クスコの神学校にいるアンドレスも、不吉な思いに貫かれていた。
アンドレスはラテン語の教書を広げたまま、遅い午後の放課後、既に授業を終えて誰もいなくなった教室の一隅で、一人の親しい友を前にして身を硬くしていた。
まるで教会の中のような厳かな雰囲気の教室の窓からは、音もなく西日が静かに射しこみ、二人の影を黒々と長くひいている。
今、アンドレスの前に座り、やはり暗澹たる表情をした友人のロレンソはインカ族の若者で、代々インカ皇帝の片腕として皇帝を助けてきた腹心の家臣の末裔でもあった。
ロレンソは理知的な大人びた雰囲気の、アンドレスと同級生の若者で、ラテン語、スペイン語、ケチュア語、キリスト教などのあらゆる学科において、その成績をアンドレスと競い合うライバル同士でもあった。
もちろん、様々な身体的な競技でも、二人はその運動神経において凌ぎを削り合う間柄でもあった。
そして、何よりも、ロレンソは物事の本質を見抜く直観力の鋭さのようなものをもっていた。
入学当初は互いに競い合うばかりだった二人も、何年間かの共同生活の中で切磋琢磨しながら互いを知るうちに、その関係性は単なるライバル同士を超えて、まるで「同志」のような間柄に変わっていた。

このようなスペイン人の厳格な監視下におかれた神学校では表立った政治批判などはもちろんタブーだったが、二人は大人たちの目を逃れては密かにその思いを語り合った。
もともとアンドレスは、特にこの学校では、自分の身の上についてあまり表立って語ることを好まなかったが、勘のいいロレンソは、二人の会話の中で、アンドレスの身の上を直観的に悟っていた。
そして、今、この放課後の教室で、ロレンソは声を低め、搾り出すように再び言った。
「噂は、やはり本当らしい。
あのブラス様が、亡くなられたという…」
アンドレスは耳を疑っていた。
ロレンソはこの神学校のあるクスコの地の出身のため、情報を入手しやすく、また、これまでもその内容が正確であることが多かった。
なお、『ブラス』とは、先日のアンドレスの館でのトゥパク・アマルらとの会合の際、スペイン国王への直訴のために海を渡る決意を表明した、あの初老の紳士である。
ロレンソは青ざめていくアンドレスの顔を直視できず、彼もまた、苦渋の表情で顔をそらした。
(まさか…!
だって、今頃、ブラス様は船でスペインに向かわれているはずだ…――)
アンドレスの心の声を察したように、ロレンソは、彼もまた非常に苦しそうであったが、再び搾り出すように言った。
「ブラス様は身分を隠してスペイン本国行きの船に乗られていたが、その船の上で何者かに殺されてしまったらしい…」
ロレンソはそこまで言うと、自分の口を押さえて、まるで嗚咽を抑えるように身を屈めた。
アンドレスは、自分の体が地中深く、どこまでも、どこまでも沈んでいくような感覚に襲われた。
何も考えられない。
呆然としたアンドレスの腕が触れ、ラテン語の教書が鈍い音と共に床に落ちた。
その教書の上に、窓から差しこむ放課後の西日は、相変わらず何事も無かったようにただ静かに注がれていた。



